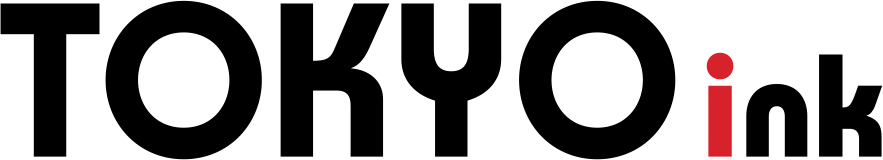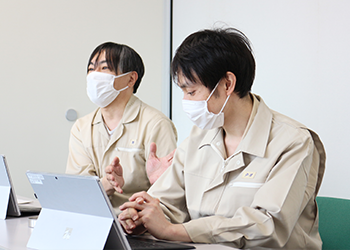まずは「自動化・省人化モデルラインの構築」を担当されているチームの開発部 大熊さん、第1課 内藤さん、岡村さんにお話を伺いました。
日本の生産年齢人口(15~64歳)は1990年代をピークに四半世紀にわたって減少を続けています。この傾向は今後も続くとされており、すでに人手不足が顕在化してきている製造業では自動化・省人化が分野に関わらず課題となっています。東京インキでは、従来より個々の工程で自動化を進めてきましたが、今回のプロジェクトではそうした既存の自動化ラインをシームレスに連携させた「完全無人化運転」をゴールイメージにモデルラインを構想。生産現場のスマート化により、より安全な労働環境を実現するとともに、これからさらに深刻化する人手不足に対応しようというもの。3年計画の半ばまで来たプロジェクトの成果、そして今後のビジョンを語っていただきました。
岡村
「『生産部署が何に一番困っているか』です。工場に行って話を聞いてみると『こうしてほしいんだよね』という生の声が聞けます。それがヒントになることが多いです。実際に起きたトラブルのリストが社内で共有されてはいますが、座ってそれを見ているだけでは何も先に進みません」
内藤
「今回のロボットは多軸で狭い空間でも小回りが利くものを選定したのですが、業者さん選びから導入までですでに1年。3年計画というと長期プロジェクトに思えますが、本当にあっという間に時間が過ぎていきます(笑)。次は制御系システムの構築。それぞれが単独で動いている設備を連携させてライン全体での自動化まで持っていくイメージです。より人の手が介在しない、より効率的な工場を目指します」
大熊
「当社の工場は三交代制で夜勤もありますので、まずは夜だけでも無人化できないか。このあたりが課題です」
続けて、「金属ナノ粒子の分散体の開発」を担当しているチームの開発部 関根さん、第2課 野崎さん、戸田さんにお話を伺いました。
「金属ナノ粒子の分散体」。とっつきにくそうな言葉が並んでいますが、実は日頃私たちが身近なところでお世話になっている、現代社会に不可欠な技術だそうです。東京インキでは、インキ事業で培った顔料分散技術を発展させたこの技術を用い、化成品分野の事業拡大を進めています。しかし、「ナノ」という単位はよく耳にするものの、一般の人には「とにかくすごく小さい」ぐらいのイメージしかありません。その小さい粒子の「分散体」とはいったい何なのでしょう?なかなか想像しづらいナノの世界、その研究開発の舞台裏を少し覗かせていただきました。
野崎
「それは...うーん、例えばある金属に人にとって便利な機能があるとして、その機能を樹脂のようなある素材に付与したい。けれど金属を混ぜたときに濁って不透明になってほしくない。完全に透明な状態を保ったまま金属が持つ機能を素材に付与したい。そうした場合にナノレベルの小ささが必要になってくるんです」
関根
「身近にあるもので言うと、パソコンやスマホの画面ってもともとは反射して見づらいものなんですよ。なので反射防止機能を付与したいわけですが、そのための物質を混ぜたら画面に色がついたり濁ったりしたというのでは本末転倒です。画面はクリアに見えないといけない。つまり『なぜ小さくしたいのか?』というと、答えは『透明にしたいから』です」
戸田
「当社の強みは、ナノ粒子に『分散する性質』を付与する技術にあるんです。もともとはインキのための技術でしたが、今は化成品などに応用して素材に付加価値を与えています」
関根
「粒子には細かくなると粒子同士が集まってしまう性質があります。そうなると濁ったり沈殿するなどして使えません。なので『細かくしなきゃいけない』と同時に『集まってくるのを阻害』しないといけないんです。こうした技術を『分散技術』と定義しています」
戸田
「特定の製品や事業はイメージせずに、その分散技術をどこまで極められるかを追求するのが開発フェーズでの課題なのですが、いくつかの物質では透明性を維持しながらそれぞれの機能を素材に付与することに実験室レベルでは成功しています。どのような応用が今後できるのかを探る段階まで来ています」
野崎
「こうした技術には、インキを紙に印刷するのと共通する部分があって、ある種の特殊な印刷と捉えることもできます。インキメーカーが進む方向として優位性のある技術だと考えています」