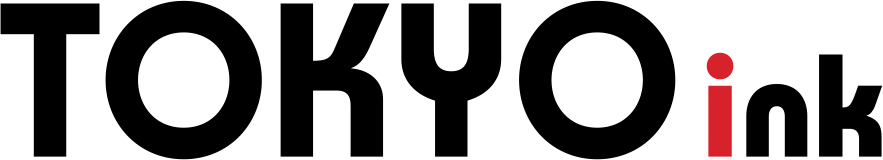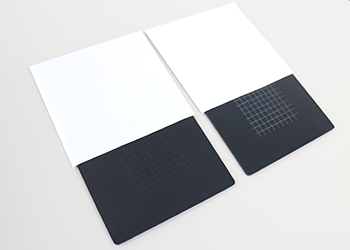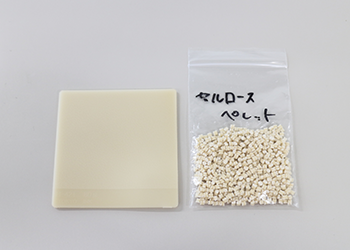今回は、営業部門化成品営業第1部の橘さん(写真中央の左)、山本さん(写真左)、藍さん(写真右)、吉澤さん(写真中央の右)にお話を伺いました。
東京インキは2023年12月に「100年企業」の仲間入りをし、次の世紀へと歩み出します。100年企業とは文字通り、100年を超える歴史を持つ企業のこと。日本には37,085社(2022年 日経BPコンサルティング調べ)の100年企業が存在しているそうですが、こうした長寿企業に共通する要素のひとつに「流行をとらえる力」がしばしば挙げられます。
と言っても、東京インキは「最終製品のための製品」を製造する中間材メーカー。「流行とどんな関係が?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし一口にメーカーと言っても、流行を生み出すメーカーもあれば、それを支えるメーカーもあります。東京インキは後者です。東京インキもまた、「流行をとらえる力」によって幾多の荒波を乗り越えてきた企業なのです。そしてその最前線にいるのが営業職です。今回は、化成品とはどんな製品で、その営業とはどんな仕事なのか伺っていきます。